結論
- 本人がやりたいと言った時が公文を始めるとき。
- そうでないなら気長に待った方が無難。
- 公文に入会す前に準備期間として毎日同じ時間に向かって何かそのときしたいこと遊びたいことを少なくとも2ヶ月は実施し習慣化する。
- 公文から自学自習を始めるのはお勧めできない。
- 自律性・有能感・関係性を常に意識にする。→(過去ブログ参照https://www.yurunikki-31.com/?p=47)
中受において公文式は少なくとも小学3年までに小6で習う国語、算数の単元を終わらせるのが定石とされている印象があります。(公文は英語もありますが中受では扱わないので今は考えていません。)
僕の子どもたちもそれに漏れず公文をさせていくつもりです。長女は年長の後半9月半ばから始めたので現在小学校入学直前の2021年3月時点で約半年です。
無理なく継続できています。そのために重要なマインドセットをお伝えします。
ちなみに進度は、
国語5A(ひらがな一文字ずつ読む→2A(ひらがなを音読→書く)所用時間8〜13分程度
算数は5A(数字を書く)→2A(一桁の足し算)所用時間平均6〜10分程度
進度、理解度はごく普通か少しゆったりめです。
今年年少になる息子はこれから長女に倣ってさせる予定でいますが今回は失敗しない公文の方を僕の長女を例に出して考えていきたいと思います。
公文はいつから始めればいい?
うちの場合は、年中くらいのときに公文式に通っているお友達が幼稚園に多く、「私もやりたい!」と自分でいいだしたのがきっかけです。
それまで僕は公文式はいわゆる塾だという認識だったのでまだ早いよとか、否、そもそも我が子に対して勉強だとか中受に興味すらなかったので、そんなふうにしか考えていませんでした。(今考えればブログまで始めてしまう始末)
だからそのときは公文に入会するに至らなかったのです。今思えばもったいなかったなと思っています💦
なので基本は本人からやりたい!と言われたときでいいのではないかと考えています。
やりたいと言う本人の意思がなくても始めていいか?
もしそうでなく親御さんだけの意思で入会させようという場合、注意が必要かもしれません。というのはうちの息子は今年年少になりますが、いつ公文を始めるか様子を伺っているのですがまだ早いと判断しているからです。
それはなぜか?
毎日、机やテーブルに座って何か学ぶ(遊ぶ)ということがまだ習慣になっているとは言えない状態だからです。
つまり、一定時間そこに座り続けられるかどうか?の一点において。
僕の両親はともに学校関係の職員でしたが母がいうには公立小学校の担任の先生よ最初のタスクは、受け持つクラスの児童を20分間座り続けさせられるどうか?だそうです。
これを聞いた時、なるほどなんて面白いんだろう!と思ってしまいました。20分間、先生はきとあらゆる手段、を高じて児童の興味を惹きつけておかねばならないと言うことですよね。
長女の場合、2歳半から当時七田式の幼児教室に通っていた背景が色濃く残っているので大丈夫だったのですが、そもそも七田式では朝学習なる習慣を大切にしていました。
簡単にいえば、教室以外ではいわゆる七田のプリント教材を毎朝行うというシンプルなものです。これを長女が2歳半のときから続けていたのでスムーズに公文に移行できたというわけです。
この毎日同じ時間に何か学ぶ(遊ぶ)という習慣が物心つく前に身につけられればまず公文式の習慣化は問題なく身につくのではないか?というのが現段階での結論です。
息子でも同じように試しているところでこれがうまくいけばより説得力が増すかもしれません。
たださっき息子はまだ公文を始めていないと言いました。それはそもそも毎日一定時間何かするという習慣が十分にできていないからです。それは気分にムラが多く、積極的なときもあればそうでない時もあるから。まあそれほ子どもですから気にしても仕方がないのですが、少なくとも今はその時期ではないとそう割り切っています。
ならば!
公文きっかけで自学自習を始めるのはどう?
公文をきっかけとして勉強習慣をつけさせればいいじゃない?と考えるかもしれませんが僕はお勧めしません。
なぜかというと、それは実は長女の失敗にあります。
あらゆる教材は成長に合わなければ子供にとって苦痛にしかならない。
先程、七田のプリントを朝学習として毎朝行うということを述べました。しかしこれは実はうまく行かなかったのです。
それはなぜか?
単純に娘にとって難しい内容だったからです。うちの子ども2人に共通することですが言葉がゆっくりで娘に関してはひらがな、カタカナもつい最近になってようやく問題なく読めてきたな、というくらいで成長速度はなんとなく周りの状況から察するに少しゆっくりペースだなと。
子供にとってこれから何年も続く勉強の始めが苦痛になっては元も子もない。どうにかしないと!と悶々としていました。でも、すぐに代替案は思いつきました。
それは何かというと、日々同じ教材(プリント)という「お勉強」は捨てる!
そして何をしてもいいよ!ということ。
ただし。
- 毎朝決まった時間に机(テーブル)に座ること
- よろしくお願いします!で始めること
- ありがとうございました!で終わること
これだけのルールで毎朝朝学習と称して2歳から公文を始めることになる5歳半まで遊んできたのです。
この毎朝起きたら机に向かう、という公文を行うという前段階の下準備が結局のところ功を奏したと強く思っています。
そもそも幼児教育に意味はあるのか?
なるほど公文など自学自習をさせる前準備としてやっていたのか、でも2歳半から5歳まで勉強しなくてもったいなくなかったか?
はい、それは最初のうちは思いましたが、気にしなくなった明確な理由があります。
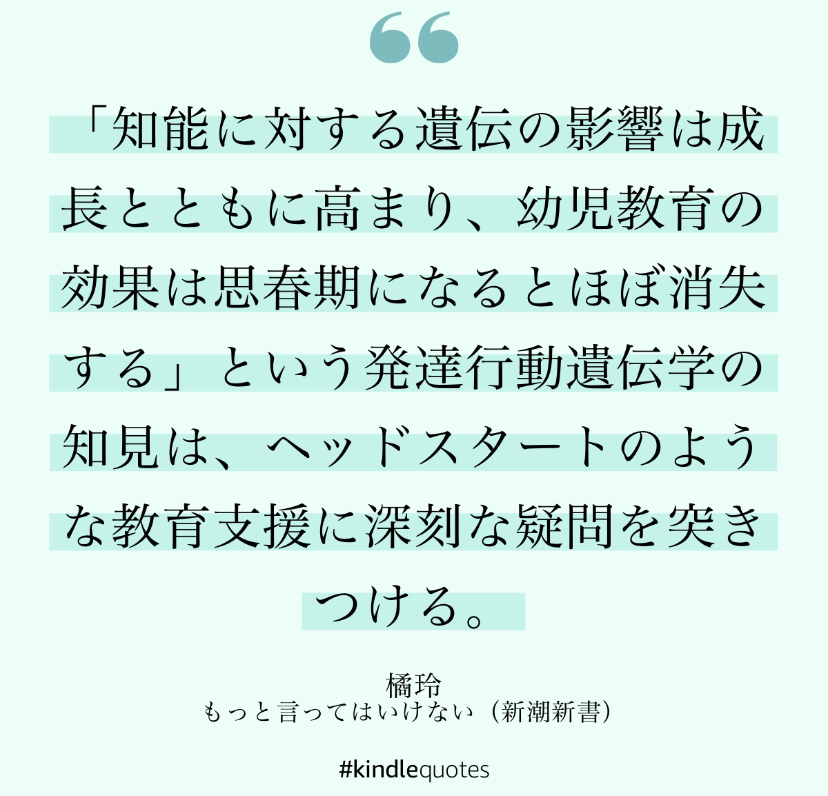
それは学力は遺伝による部分が大きく、しかも幼児教育の優位性は小学校低学年までしかない、言い換えれば幼児教育が報われるのは小学校までだということを知ったからです。
つまり、勉強させたくて行ういわゆる幼児教育そのものにはあまり意味なんてない。少なくとも頑張れば報われるという範囲は限定されている。
しかし日々の習慣づくりはどうでしょう。ロンドン大学の研究によれば人(21から〜45歳対象)はそれを習慣にするためには平均66日要するとのこと。これがそのまま幼児期未就学時期の子どもにそのままに当てはめられるわけではありませんが、少なくとも成人した親御さんには十分当てはめられる研究結果でしょう。
つまり、勉強をするための前準備、つまり【毎日決まった時間に一定時間楽しみながら机に座り続けること】こそが未就学期に置いては最優先されるべきことだという結論に至ったというわけです。(これについての具体的な方法は過去ブログをご参照ください→https://www.yurunikki-31.com/?p=47)
異論あると思いますが、僕はこの考え方をしばらく採用していくつもりです。
あなたはどう考えますか?
勉強すれば報われるはずだと未就学時から勉強させるもよし。
遺伝によって得意なこと不得手なことがあるのだと知り、日々模索していくことが僕にとっての今のところ最適解です。
ご参考になれば幸いです。
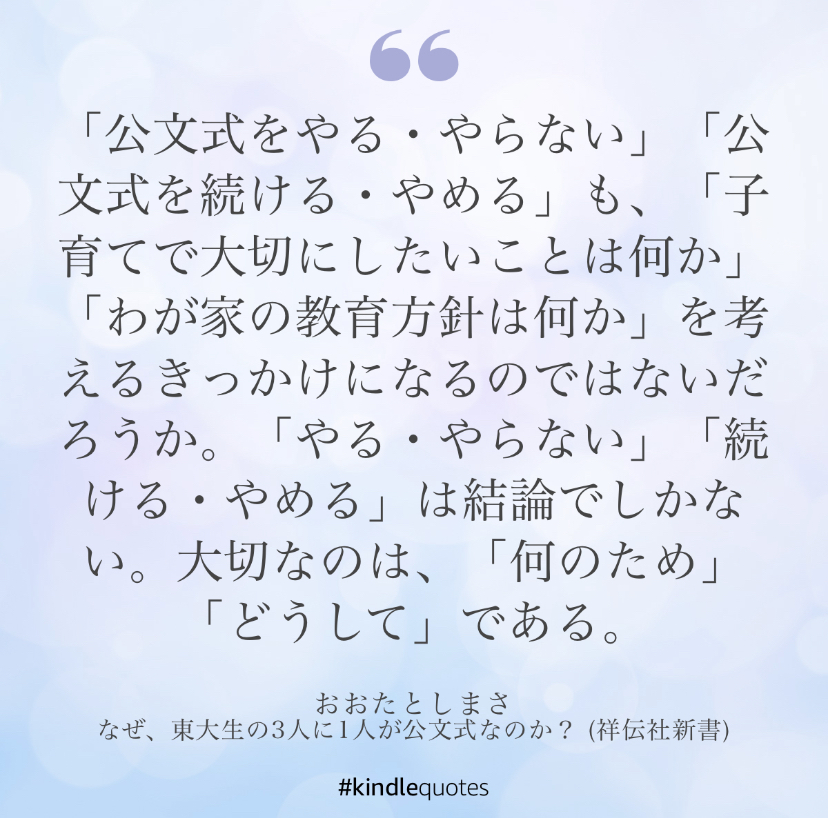


コメント